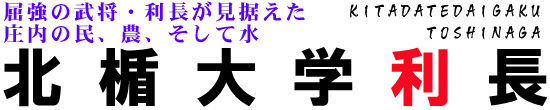 |
| 庄内平野を見はるかす高台、庄内町立川地区楯山公園の一角に、北楯大学利長の像がある。ここは昔狩川城であった城址である。像は両刀を腰にさして手を組み、遠い彼方に眼を据えている。利長の視界には、平野の中央を悠々と流れ下り、日本海へとむかう最上川があるだろう。そして眼下には、利長自身が心血を注いでつくりあげた水路とその支流、その恵みを受けて美しく広がる水田とその中に点々とかたちづくられた多くの新田集落がある。そしてもう一つ、今新しい町の力となって暮らしの中にある白い風車が、自然と人との共同の英知を物語るように回っている。 利長の像の後方には北楯大学利長を祀った北楯神社が建っている。安永七年(一七七八)利長の偉業をたたえ、遺徳を仰ぐ地元民や農民によって、利長を御祭神とする水神社を八幡宮の境内に建立し、北楯水神として祀った。その後、大正八年(一九一九)には城址に独立した社となって移築され、社名も北館神社と改めた。昭和四七年(一九七二)現在の地に新築され、森につつまれた荘厳な趣をたたえている。  社内には建立当時から御神体として祀っていた大学利長の木像や、利長がいく度となく戦場にたずさえて行った自身着用の鎧、また利長の主であり山形の城主である最上義光から届いた書状、そして「北楯大堰」の実測図など、貴重な品々が保存されている。 社内には建立当時から御神体として祀っていた大学利長の木像や、利長がいく度となく戦場にたずさえて行った自身着用の鎧、また利長の主であり山形の城主である最上義光から届いた書状、そして「北楯大堰」の実測図など、貴重な品々が保存されている。さて、北楯大学利長とはどんな人物であったのだろう。今日一般では”利水家”として名を知られる通り、庄内地方の最上川以南の農業は利長なくしては語れない存在であるが……。 慶長五年(一六〇〇)の関ケ原の戦いで、山形城主最上義光は庄内の3郡、狩川、清川、立谷沢を領有することになった。義光は慶長六年これを家臣の北楯大学利長に3,000石として与え、利長は狩川領主となって庄内におもむくことになったのである。利長53才の年であった。利長は入部直後領地の検分を行って治政の第一歩を踏み出した。領域は一見、大小の川が流れていて農業用水の心配はないと思われた。しかし大河に接していながら水利に恵まれず、むしろ最上川の氾濫や低河床という地形上の特徴がもたらす潅漑不能、防堤の不備などによって水田は廃退し、時に大きな災害をもこうむっている土地であることを知らされたのである。 |
|
Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved. |