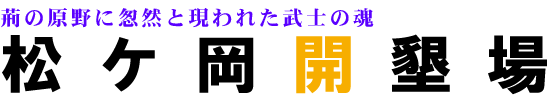 |
 城下町鶴岡市の市街地を離れて、松ヶ岡への一本道に入ると、真正面に月山がその胸をあけ放つように座っている。松ヶ岡は出羽三山のふところに分け入るなだらかな丘陵の裾野にあって、水田と果樹の畑が広がる台地の中に集落をなしている。この中央部に全国一の大きさを誇る蚕室5棟が、高く甍を揚げて建っている。国指定史跡をうけて、益々風雪の歴史を想い起こさせる風格をおびている。現在も松ヶ岡開墾記念館として、貴重な歴史資料や北海道開拓資料、あるいは数千点に及ぶ日本全国の土人形が展示されている。また別棟では陶芸教室や各種の展覧会に開放されたギャラリー、御食事処となって活用されている。敷地内には庄内の米づくり農具収蔵庫が建設されて、一帯は庄内の開墾と稲作にまつわる土の香のする宝庫である。 城下町鶴岡市の市街地を離れて、松ヶ岡への一本道に入ると、真正面に月山がその胸をあけ放つように座っている。松ヶ岡は出羽三山のふところに分け入るなだらかな丘陵の裾野にあって、水田と果樹の畑が広がる台地の中に集落をなしている。この中央部に全国一の大きさを誇る蚕室5棟が、高く甍を揚げて建っている。国指定史跡をうけて、益々風雪の歴史を想い起こさせる風格をおびている。現在も松ヶ岡開墾記念館として、貴重な歴史資料や北海道開拓資料、あるいは数千点に及ぶ日本全国の土人形が展示されている。また別棟では陶芸教室や各種の展覧会に開放されたギャラリー、御食事処となって活用されている。敷地内には庄内の米づくり農具収蔵庫が建設されて、一帯は庄内の開墾と稲作にまつわる土の香のする宝庫である。ここ松ヶ岡から発した近代日本の原形を、西郷隆盛が庄内の開墾士に贈った書に因んで命名され編まれた『凌霜史』と『松ヶ岡開墾史』から読みとることにしたい。 松ヶ岡の歴史、または開墾の歴史は、全て明治時代誕生の動乱期とその顛末から始まっている。慶応四年(一八六八)、鳥羽伏見の戦いに始まった戊辰戦争(内乱)は、明治二年(一八六九)五月北海道函館五稜郭開城で終息したが、庄内藩のこの戦いは東北諸藩最後の降伏開城となり、慶応四年九月、すでに半年にわたる内戦を終えた。明治新政府は旧藩兵の解体と廃藩置県を行い、また各県の行政執行についても旧士族の専任を廃して広く民間から登用する政策をとった。そのため、旧諸藩の武士たちは職を失うことになり、加えてこれまでの家禄制も段階的に廃止されようとしていた。近く封建武家社会はほぽ完全に終焉を迎えようとしていたのである。 |
|
Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved. |