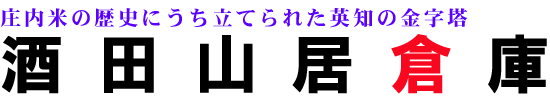 |
 北に鳥海山、東に出羽丘陵、南には朝日山塊と摩耶連嶺があり、西を日本海にひらいている庄内地方。太古、この地は内湾であったという。ここに吾妻連峰を源とする急流最上川と日向川や、北上して海に注ぐ赤川などの河川がある。こうした川が運んだ土砂は肥沃でゆるやかな扇状地をつくり、さらに土地の隆起が加わって庄内の台地が生まれた。日本海からの強い風と波が広大な砂洲をもたらし、海湾から発達した低湿地帯は扇状地と合いまって庄内平野ができたといわれる。弥生時代の農耕文化を迎える時期にあってこの大地は稲作に適した地盤になっていたのである。 北に鳥海山、東に出羽丘陵、南には朝日山塊と摩耶連嶺があり、西を日本海にひらいている庄内地方。太古、この地は内湾であったという。ここに吾妻連峰を源とする急流最上川と日向川や、北上して海に注ぐ赤川などの河川がある。こうした川が運んだ土砂は肥沃でゆるやかな扇状地をつくり、さらに土地の隆起が加わって庄内の台地が生まれた。日本海からの強い風と波が広大な砂洲をもたらし、海湾から発達した低湿地帯は扇状地と合いまって庄内平野ができたといわれる。弥生時代の農耕文化を迎える時期にあってこの大地は稲作に適した地盤になっていたのである。庄内地方で発掘された多くの遺跡は、弥生前期には稲作が始められていたことを物語っているし、また水田の開発も平安時代まで急速に進んだ。しかしその後は多くの湖沼がそのまま残っていたため開田耕地の適地が少なくなり、大規模な水利事業を待たなければならない時代に入ったのである。農業水利事業を待たなければならない時代に入ったのである。農業水利事業と耕地再開発はおよそ200年後のことになったのであった。時代は下って荘園形成の頃から武士社会の隆盛をみる時期に、庄内地方の稲作は本格的な基幹産業となっていた。同時に日本海海運と最上川をはじめとする大小の河川を利用した船運が活発になり、遠く阪神地方や関東、そして太平洋岸各地との交易が促されるようになってゆくのである。そうした中で、米もまた生産地でそのまま消費される時代は過ぎ、戦国の世が終りを告げようとする頃、酒田湊から米の積み出しがあったとする記録が残されている。天平十六年(一五八八)豊臣秀吉の小田原攻めが開始し、その折諸国の米が出征軍に送られたが、酒田から庄内米を回漕したのは2年後の天平十八年(一五九〇)であった。この時は日本海沿岸を通って下関に達し、瀬戸内海を抜けて大阪に運び込まれたという。 |
 |
|
Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved. |